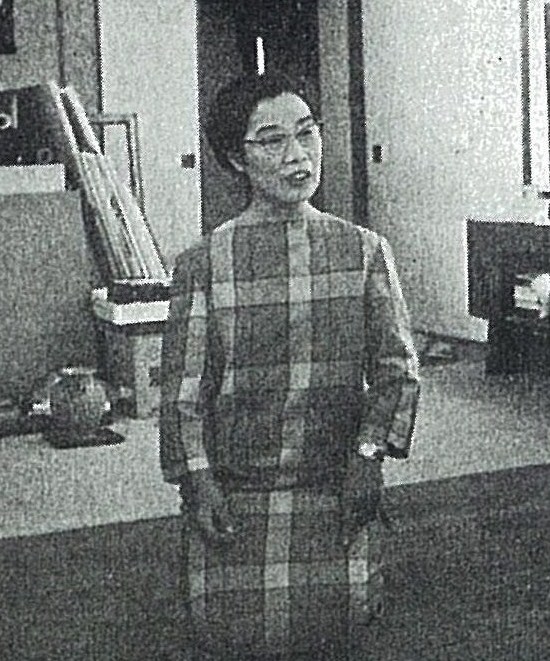記事
日本における洋画の歴史と
明治から戦前にかけての
女性洋画家たち
日本で近代化=西洋化が推し進められた19世紀後半、美術の分野においても、西洋の概念や技術が急速に取り入れられた。その過程で、「美術」や「絵画」「彫刻」「工芸」といった言葉も、西洋概念の翻訳として成立していった。もちろん、それ以前の日本においても、これらの語に相当する言葉や技術は存在していたが、明治初期に西洋の概念に対応するものとして再編され、今日に至る。そして、明治10年代(1882–1887年)に入ると、西洋からもたらされた油絵や水彩の技術である「洋画(西洋画)」と、もともと日本にあった伝統的な画法である「日本画」というジャンル概念が現れはじめる。「西洋」に「日本」を対置したこの相対概念は、西洋美術に対する日本美術の葛藤を端的に示している。
最初に「日本画」の語が現れたのは、お雇い外国人として来日し日本美術に関心を寄せたアーネスト・フェロノサ(1853–1908年)が1882年に龍池会で行った講演「美術真説」で使われたJapanese paintingの翻訳語としてであった。やがて、明治20年代(1887年–)に入り、国家体制の確立と並行して美術の制度化が進められ、「日本画」と「洋画(西洋画)」というジャンルが成立してゆく。社会学者で帝国大学教授の外山正一(1848–1900年)が1890年に同大学で行い、大きな論争となった講演「日本絵画の未来」では、当時の日本の絵画が「日本画」「西洋画」の二大流派の五里霧中にあるとされた。また、伝統的日本美術の保護を目的に岡倉天心(1863–1923年)とフェロノサの主導により1887年に設立された東京美術学校(現・東京藝術大学)では、1896年に「西洋画科」が新設される。やがて、明治40年(1907年)に政府が開設した官展である文展(文部省美術展覧会)に「日本画」「西洋画」の両部が設定されたことで、両者は制度的にも定着していった。今日では、大半の日本の美術館において、コレクションの分類として、「日本画」「洋画」という区分が設けられている。
ところで、今でこそ「洋画」というと、明治以降の日本で独自に発展した油彩画、というニュアンスが強いが、当初は「西洋画」という呼称からも分かる通り、西洋の絵画という意味合いで用いられていた。日本人の画家が油彩で描いた作品は、どこか借り物の技術と見られていた節もあったのではないだろうか。この葛藤は長く続き、明治から大正、昭和にかけて、美術教育や美術協会、美術展の区分の名称で「西洋画」と「洋画」は混在し続ける。「洋画」が、日本の近代美術における独自のジャンルとみなされるようになったのは、第二次世界大戦後のことである。
ここまで、「洋画という」言葉の成り立ちを見てきたが、実際の油彩の技術はどのように日本にもたらされたのだろう。本格的に油絵が学ばれるようになったのは、幕末に幕府が洋風の技術の研究を始めたときからである。1857年、徳川幕府は蕃書調所に絵図調方を置き、川上冬崖(1828–1881年)が絵図調出役となる。1862年には高橋由一(1828–1894年)が入所し、画学研究は少しずつ進んでいった。高橋は、のちに五姓田義松(1855–1915年)らとともに、幕末期に記者として来日した画家のチャールズ・ワーグマン(1832–1891年)に油彩画を学んだ。1868年の明治維新を経て、明治初期には、国沢新九郎(1848–1877年)、川村清雄(1852–1932年)、やや遅れて山本芳翠(1850–1906年)らがヨーロッパに渡って現地で油彩画を学んでいる。
1876年には、日本最初の美術教育機関である工部美術学校が設立される。「画学科」と「彫刻科」の二科が設置され、イタリアから招かれた画家アントニオ・フォンタネージ(1818–1882年)と彫刻家ヴィンチェンツォ・ラグーザ(1841–1927年)がそれぞれ教師を務めた。工部美術学校は設立後まもなく女子学生の入学を許可しており、フォンタネージのもとでは、山本、五姓田、浅井忠(1856–1907年)、小山正太郎(1857–1916年)、松岡寿(1862–1944年)らとともに、山下りん(1857–1939年)や山室政子(1858–1936年)、秋尾園(1863–1929年)、須川蝶(生没年不詳)、大島雛子(生没年不詳)、川路花子(生没年不詳)、神中糸子(1860–1943年)らが学んだ。早い時期に女子学生が入学を許可された背景として、欧米での女子教育水準の高さを目の当たりにした明治政府が、男子と同じく女子の教育にも力を注ごうとしたことが考えられる。もっとも、それは今日的な平等教育の理念ではなく、男子を育てる母親が無学であってはならないという理由ではあったが、明治初頭には、1872年に開校した官立の東京女学校はじめ、公立や私立の女学校の設立も相次いだ。こうした時代の追い風があり、工部美術学校にも女子学生が迎え入れられたのだろう。
女子学生たちは、男子と教場こそ分かれていたものの、フォンタネージの方針のもと、同男子と同等のカリキュラムを受講していたようだ。しかしながら、1878年にフォンタネージが辞任すると、結婚や病といった事情、あるいは後任の教師への不満から女子学生たちは次々と退学していき、女子修了者は一人も輩出されない結果となった。退学後の彼女たちの境涯には、この時代の女性が画家として生きる困難が現れているように思われる。富裕な令嬢であった大島と川路は、もとより絵を生業にしようという意思はなく、上流婦人の最新教養として油彩を学んでいたようだ。また、正教会に入信することでニコライの援助を得ていた山室は、結婚および妊娠のためロシア留学を断念し、夫の岡村竹四郎(1861年–没年不詳)と印刷会社を創立し、石版画家として活躍した。秋尾は写真師中島待乳(1850–1938年)と結婚し、夫の幻灯機製造を助けて、下絵、彩色に従事した。
工部美術学校に学んだ女子学生の中で、生涯家庭に入ることもなく、画業に専心したのは山下と神中である。山室の誘いで在学中に正教会に入信していた山下は、山室に代わってロシア留学を果たし、2年間サンクトペテルブルクに滞在して女子修道院でイコンの技術を学んだ。帰国後は東京神田にあった日本正教会の女子神学校にアトリエを構え、外界との接触を断って制作に没頭し、300点あまりのイコンを残している。神中は、退学後小山に師事し、工部美術学校を去った小山や浅井らが結成した洋画研究会である十一会(のちの明治美術会)に参加、内国勧業博覧会に出品したり、文展に入選を果たすなど、女性洋画家の先駆者の一人として活躍した。ちなみに、官展設立以前の洋画家たちの作品発表の場として大きな役割を果たした明治美術学会には、詳細は不明だがかなりの数の女性作家が出品していたようである。
また、工部美術学校には学んでいないが、彼女たちと同世代で、洋画家として生きた女性として渡辺幽香(1856–1942年)と清原玉(1861–1939年、のちにラグーザと結婚しラグーザ玉)の存在も忘れてはならない。渡辺は、ともに洋画家である五姓田芳柳(1827–1892年)を父に、五姓田義松を兄にもち、父親の工房で兄から洋画を学んだ。生涯結婚はせず洋画に専心したいという願望を抱いていたが、父の命で同門の画家と結婚。しかし、結婚後も内国勧業博覧会に出品したり、版画を学んで西洋人向けの日本風俗画集を出版したり、シカゴ万国博覧会婦人館に出品したりと、精力的に活動を続けた。また、華族女学校や女子高等師範学校の教師を務めるなど、後進の育成にも携わっている。他方、清原は1877年にラグーザと出会い、彫刻のモデルをつとめ、絵の指導を受けるようになる。1880年にラグーザと結婚し、2年後イタリアに渡ってパレルモ大学美術専攻科に入学。デッサンと油彩画を学び、やがてイタリア国内やヨーロッパ各地の美術展に出品。1927年にラグーザと死別し日本に帰国した後も、各地に写生旅行に赴くなど、画業に専念した。

森田元子《想い》1947年、油彩、キャンバス、90.8×80 cm、東京国立近代美術館 © MOMAT / DNPartcom

有馬さとえ《赤い扇》1925年、油彩、キャンバス、73×53 cm、所蔵:東京国立近代美術館蔵 © MOMAT / DNPartcom
工部美術学校は1883年に廃校し、その後1887年に設立された東京美術学校は女子の入学を許さなかった。ようやく男女共学となるのは、戦後1945年になってからのことである。関西における京都絵画専門学校(1909年設立、現京都市立芸術大学)も同様に、1945年まで女子の入学を認めなかった。20世紀の前半、画家を志す女子学生たちを受け入れたのは、1901年に開校した女子美術学校(現女子美術大学)である。当時の女子の中高等教育では「良妻賢母主義」が謳われていたが、女子美術学校は女性のための職業専門教育を目指すものであった。創立発起人の一人となった横井玉子(1855–1903年)は、20歳の若さで夫を失った後、いくつかの女学校で教員をつとめながら、浅井や本多錦吉郎(1851–1921年)から水彩画や油彩画を学び、のちに明治美術会や白馬会にも入会している。教員として働く中で、女性の地位向上と自立のために女性の教育者を養成する必要性を痛感したこと、彼女自身が美術に強い関心を抱いていたことが、計画を推進する大きな力となったことだろう。東京美術学校の彫刻の教授であった藤田文蔵(1861–1934年)らの協力を得て開校した女子美は、資金不足に直面し、たちまち廃校の危機に陥る。美術というだけでも特殊であった時代に、女性のみと謳った学校に対して、周囲の目は冷ややかであった。それを救ったのが順天堂院院長、佐藤進男爵(1845– 1921年)の婦人、佐藤志津(1851–1919年)である。彼女もまた女性の地位向上を希求する女性の一人であり、横井から援助を求められて再建に力を注ぎ、今日の礎を築いた。
東京美術学校教授の男性画家が講師として迎えられ、やがて卒業生が専任教授となる道が開けてゆく。授業では、石膏像や生きたモデルを囲んでのデッサンも行われており、人体デッサンの基礎を学ぶことができたようだ。初期の卒業生で画家として活躍した亀高文子(1886–1907年)は、女性洋画家として文展でいち早く褒状を受け、出品を重ねた。亀高は、女性画家の初の公募団体である朱葉会の創立にも参加している。また、1916年から講師を務めた岡田三郎助(1869–1939年)のもとからは、森田元子(1903–1969年)、深沢紅子(1903–1993年)、三岸節子(1905–1989年)、甲斐仁代(1902–1963年)ら、のちに官展や二科展など画壇で活躍する多くの女性画家が巣立っている。岡田は私立の画塾である女子研究所も主催しており、有馬さとえ(1893–1978年)や、森田、三岸、桂ユキ子(ゆき)(1913–1991年)も一時期ここに学んだ。最後に、戦前に女子美で学んだ画家として、赤松俊子(丸木俊)(1912–2000年)の名も挙げておこう。こうして同校で学んだ画家たちの名前を並べてみると、女性画家という枠を超えて、大正から昭和にかけての洋画を牽引した画家が多かったことが分かる。しかしながら、同時代の男性作家に比べて、彼女たちの調査研究や評価はまだまだ不十分であり、今後の課題である。
横山由季子
東京国立近代美術館研究員。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程満期退学。 パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校美術史・表象文化史研究科留学。世田谷区美術館学芸員、国立新美術館アソシエイトフェロー、金沢21世紀美術館学芸員を経て現職。日仏の近代美術を専門とし、近年では日本近代の女性画家について研究を進めている。