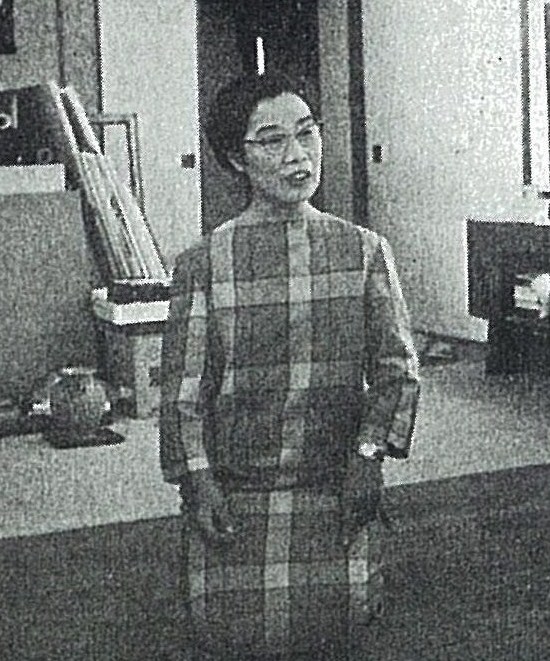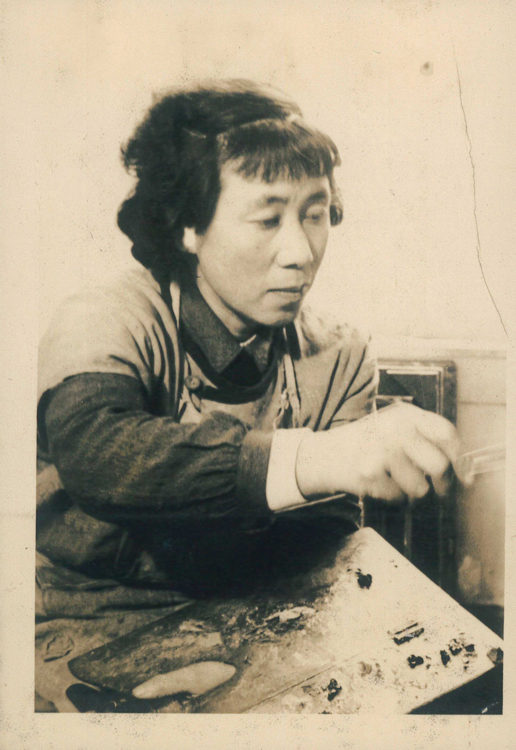日本人アーティスト
大学で文化人類学を学び、1974年そのフィールドワークで沖縄に行き、そこで島ごとに違いのある琉球藍の製造過程を調査し、2年間滞在して染めと織を研究する。この経験を基礎として、1992年から色彩豊かなファイバーワークの作家として活動を始めるが、1995年の阪神淡路大震災の経験を転機として、社会的視点を作品の根幹に据えた作風に転換する。
1998年大阪トリエンナーレ1998で、デュッセルドルフ市・関西ドイツ文化センター特別賞を受賞、その副賞として1999年にデュッセルドルフにアトリエを与えられて滞在し、個展を開催。これをきっかけに以後、ドイツと日本を行き来しながら制作活動を行う。
井上はこの頃から隔離された人間の心の痛みや、人と人を隔てる境界をテーマにした作品を制作。それはまず精神科病院の内部と窓のモノクロ写真によるインスタレーション《不在Absence》(1997–2001年)として、東京とドイツで発表された。その後ドイツの映像制作チームの一員として、アラスカやイエメンなど世界を回る経験を重ねた後、目を閉じて立つ思春期の子供たちの3/4半身の肖像写真によるインスタレーションを、まずはモノクロ写真で《汝 何を欲するか What Wilt Thou》(2003年)と題して、東京、名古屋、ムルハイムで発表。今まで隔離施設の室内の写真を、人の姿を入れずに撮ってきた井上が、初めて人間の肖像を撮ったのは、撮影のために世界各地の辺境地帯などを訪れた際に、様々な地域においても変わらず、地域の紛争やDVなどの犠牲となるのは子供たちであることを実感し、その姿を留めておきたいと願ったからだという。
2005年には文化庁文化交流史に任命され、ウィーンに1年間滞在して制作。その成果として2005年、ウィーンのオットー・ワーグナー精神科病院内のユーゲントシュティール・テアターで個展《Inside-Out》(2005年)を開催。これは目を閉じて立つ世界各地の高校生のカラー写真と窓の写真によるインスタレーションであった。この作品は評価されてウィーン美術館Wien Museum MUSAに収蔵され、同シリーズはその後もドイツや日本でも展示された。また井上がそれまで訪れた各地の施設で撮りためた、日本やウィーンの精神科病院、ドイツの少年刑務所、サナトリウムの窓、ナチの強制収容所跡などの室内や窓のカラー写真も、同じく《Inside-Out》と題して発表し、同題の写真作品集を出版している(2009年)。
さらに2011年の日本の東日本大震災の後、ドイツと日本の森の写真によるインスタレーション《Mori:森》(2011–2012年)を制作。ドルトムントでの個展と日本の4つの美術館を巡回した「アジアをつなぐ:境界を生きる女たち1984-2012」展Women In-Between: Asian Women Artist 1984-2012で発表した。ここで井上が撮影した森は、ドイツの廃坑になったルール炭鉱付近の人工林や第二次大戦の激戦地となったライヒスヴァルトの森であり、日本では、現在、井上が住む奈良の、国造り神話に遡る太古の森と、東日本大震災の被災地、三陸海岸の松であった。すなわちそれぞれ固有の物語と歴史を持つ風景であり、見る者はその風景の背後の歴史的記憶を蘇らせるように促される。《Mori:森》はその後、オーストリア国立工芸美術館MAKに収蔵された。
そして2014年からは生命の根源である水をテーマに制作を始め、2016年、モノクロの写真作品《MIZU》シリーズ(2016–2024年)として発表。これはドイツのルール地方にある火力発電所で撮影されたもので、銀色の「雨」は有害物質を含む冷却水のシャワーであり、命を育む自然の雨とは対極にある水であった。豪雨のようにザーザーと落ちる冷却水の情景は映像でも撮られてともに展示された。そして2023から2024年、井上はベルリンの難民キャンプに通い、ウクライナや中東からの難民の女性たちと交流を重ねて、彼女たちの肖像写真を撮影した。この新作《Being in the face》は早速、デュッセルドルフ市立美術館に収蔵され展示された。
「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム
© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2025