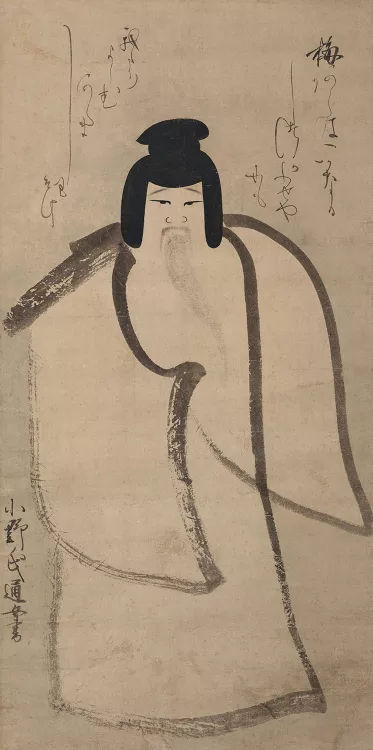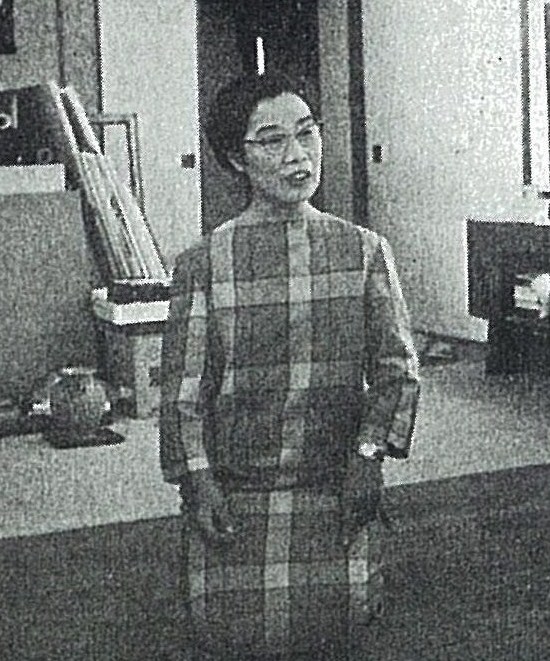記事
女性の日本画家と美人画
*この記事は、「江戸時代から20世紀初頭までの女性画家の芸術教育」の続きです。
2.女性美人画家誕生
京都では、東京美術学校より早く1880年に京都府画学校が設立され西洋画を含む絵画教育が始まっていた。当初女性も入学可能であり、後に美人画家として最も有名になる上村松園(1875-1949年)は1887年に12歳でここに入学し、すでに著名な画家であった鈴木松年に師事した。松年が翌年学校を辞めると、その画塾に入門し、歳上の男性たちに混ざって修行を積んだ。このように松園は画家とは関係の無い家に生まれたが、男女別学が定着する直前に美術学校に入ることができたことにより有利な学習環境を得た。晩年の談話をまとめた『青眉抄』(六合書院、1943年)によれば、小さい頃から人物を描くことが好きで、最初に手本としたのは絵草紙屋で売っていた浮世絵や夜店で売っていた絵入りの版本、武者絵、役者絵、貸本屋で借りた読み本の北斎の挿絵などだったという。小学校のときには女性の絵ばかり描いており、画学校での椿や木蓮などの花の一枝を手本どおりに描き、鳥類、山水、樹木、岩石と進む画学校の教育には不満があったという。後年の松園の美人画の作品の中に浮世絵から主題や構図を取り入れている例が数多くみられることが指摘されている。その後も古画の展示会や1897年に帝国京都博物館(後に帝室博物館)が京都に開館すると通って独学した。
松園も小蘋のように展覧会によって成功への足がかりをつかんだ。1890年、第三回内国勧業博覧会に出品した作品を来日中のイギリス王室のコンノート殿下が購入し、これが新聞に報道され評判となった。これによってシカゴ・コロンブス博覧会の女性館展示品を農商務省から依頼され、画家としての自信をつけた。文展でも1907年の1回展から若い女性たちを描いて受賞を続け、その後も帝国美術院展覧会(以下帝展)の重要作家となった。やがて増加する女性画家たちよりも年齢も上であり、早くから活躍したことで、別格の存在となった。松園自身、画家を志してからは女性らしく着飾ることを否定しており、シングル・マザーであったが家事、育児は母などがおこない、ジェンダー的には男性画家と言ってよい仕事ぶりだった。
一方、松園より13歳若い榊原(池田)蕉園(1886–1917年)は東京の裕福な家庭に生まれ、女学校で女子教育を受けた世代に属する。その点が上村松園との大きな違いである。父は実業家、母も趣味で洋画を学んだ。蕉園の談話記事「私の今日あるは全く師の賜」(『婦人画報』51号、1911年1月)によれば、1901年に水野年方に師事するが、それは学業の傍ら「琴、茶湯、挿花などの稽古もせなければならぬ」なかでのことであった。こうした技芸は近世には主として男性の教養であったが、この頃には、良家の若い女性が身につけるべき良き趣味とされていた。蕉園も絵が好きで「小学校時代から雑誌や新聞の挿絵を見ては時々それを写したりして居りました」と述べており、松園よりは新しい時代になるが、やはり雑誌口絵の版画や新聞挿絵を模写して人物を描こうとしていた。父が福沢諭吉門下の実業家であったから福沢諭吉が創刊した『時事新報』を購読していたならば、岡村政子が原画を描いた石版刷りの新聞附録の女性像を見ていた可能性があるだろう。
母が洋画を習っていたにも関わらず蕉園が水野年方に入門したのは、年方が人物画の挿絵を多く描いていたからであろう。同門の鏑木清方、夫となる池田輝方も後に美人画家となった。そして蕉園も1回文展に《もの詣で》(図4)が入賞し、人気画家となった。澤田撫松「閨秀画家榊原蕉園女史」という特集記事が『婦人畫報』(9号、1908年3月)に掲載され「最も若くして而かも最も群を抜いて居る者を求めると、榊原蕉園女史より外にはない」と書かれるほどとなった。蕉園は「先生に始終『人間を寫すので、人形を畫くのでは無い。繪は精神気品が大切だから、其事を忘れてはならぬ』と申されました」と述べており、人物の内面を深めるように促されている。蕉園も展覧会によって著名となり、先輩の松園と並ぶ存在となった。
やはり美人画家となる栗原玉葉(1883-1922年)はもともと貸本屋から借りた小説本の口絵を写していたという。6この時代には武内桂舟、富岡永洗、水野年方といった画家たちが人気の挿絵画家であったが、あるいはもっと古いものを見ていたかもしれない。1907年に女子美術学校に入学するが、教師からは人物画を描くことを嫌がられたと言い、学校の参考品が十分ではなく、博物館や図書館で古い名画を写して人物画を独学した。そうしたなかでも特に子供の絵を描くことを好んでいた。
このように美人画家として人気を博すことになる女性たちは、幼少期から大衆的な出版物を手本に自発的に女性や子供の絵を描いた。このことは彼女たちの生活のなかに、すでに家庭での性別役割分担が浸透していたということであろう。そしてまた、彼女たちが画家の家に生まれていなかったため、明治初期には狩野派や南画に比べて浮世絵や挿絵を「俗」なものとみなす絵画のヒエラルキーがあったことを学ばず、自由に描けたことも重要である。後に松園は浮世絵と比較されることを嫌うが、水野年方から蕉園への「繪は精神気品が大切だ」という教えも、浮世絵の系譜に連なる年方自身が人物画を「俗」とみられることに警戒感を持っていたからであろう。
3.美人の表現
・上村松園
松園がほぼ無背景の画面に若い女性を大きく描く美人画のスタイルを築くのは《人生の花》(1899年、京都市京セラ美術館)の頃からである。《人生の花》は結婚当日、婚礼衣装の若い女性がうつむきがちに母の先導で結婚相手の家に向かう様子を取り上げたもので、同様の作品が複数残されていることから人気の主題であったことがわかる。画面に女性だけを描く先例は、前述の野口小蘋も描いており、この頃には京都在住であった。また京都で多くの日本画家を育てる幸野楳嶺や森寛斎も妓女を描いている。松園の作品が新しい点は芸妓ではなく普通の家の若い娘を描いている点である。そして家から家に嫁ぐ若く従順な女性は、明治政府が推し進めた家父長制に沿う主題である。絵を見る女性が若ければ花嫁に、年配であれば母親に、感情移入することができる。女性画家たちは男性だけでなく女性たちにも支持される作品を描いたことで一層の人気を博した。
上村松園は浮世絵や古画を見て勉強したと回想していたが、それだけでは立体的な人物表現ができるようにはならない。1900–1901年にヨーロッパ視察留学をした日本画家竹内栖鳳は帰国後、モデルを呼んで弟子たちとともに人物画に取り組んだ。松園は栖鳳の渡欧以前に師事しており、時期は不明だが栖鳳の画室で下絵を模写したという。おそらく松園も帰国後の栖鳳による人物研究から学ぶところがあっただろう。
池田蕉園による《春の日》は、若い女性が編み物を手に幼い妹の世話をしながら春の日を楽しんでいる図である。編み物は近代になって紹介された新しい手芸である。当時女性たちが求められた性別役割に合致する主題である。少女の手の指などの表現には立体描写がみられ、西洋画の人体表現にも学んでいたであろう。先に述べたように蕉園は石版画の人物画も見ていた世代である。またフランスでアカデミスム絵画を学んだ岡田三郎助ら洋画家たちが戸外の自然と女性を組み合わせた作品を描くようになっており、蕉園もそうした作品から刺激を受けた可能性があるだろう。岡田は理想化された人体を描く技術を日本人に応用し、豪華な着物を着た若い女性像を発表した。それらはポスターや新聞附録、雑誌口絵などによって広まった。女性雑誌の口絵も多く担当したことから、女性にも人気があったとみられる。岡田は東京美術学校教授で女子美術学校教授も兼任しており、岡田による女性像を日本画家たちも参照したであろう。
・文展
文展には回を追うごとに多くの観衆が押し寄せた。また会場で作品の購入申し込みができたことから、収集家たちが初日に訪れて購入を競った。1912年の6回文展では36日間の入場者数が16万人を越え、1917年の11回文展では36日間に24万人以上が入場した。売約となった点数は、池田蕉園が最多であり、上村松園、河崎蘭香、栗原玉葉、島成園、ら女性の美人画が続いた7。男性画家では池田輝方と鏑木清方が人気であった。
1915年1月号の『日本美術』(17巻3号)は「閨秀作家号」として発刊され、文展で人気の女性画家たちの作品写真が巻頭を飾った。それぞれが異なる学習を経てきた画家であるが、松園の《舞仕度》、栗原玉葉《噂のぬし》をはじめ、ここに収録されたどの作品の女性も、ふっくらとした顔に眉を太めに少し下がり気味に描かれ、両目はやや離れ、まつげは濃く、黒目が大きい顔立ちである。女性画家たちの女性表現に、いわば共通の「型」ができていたことがわかる。おそらく文展に集まる一般の観衆からこうした表現が支持されていたことによるのだろう。「閨秀作家号」の記事、若月松之助「女流作家の価値」では、1905年の日露戦争終結後のナショナリズムの高まりの中で人々が豪華なものを求め、その「機運に乗じて盛んに美人を描き、濃艶な色彩を盛り上げて観者の眼を奪ったのは即ち女作家であった」と指摘している。
1914年に勃発した第一次世界大戦による大戦景気も後押しし、幸せそうな若い女性や子供を描いた作品は益々人気を集めた。坂井犀水も『美術新報』の記事のなかで「婦人を主題とするもの、特に家庭的事相を題目とするものは、最も閨秀作家に適當なる畫題であると思ふ」と述べている。8
1915年の9回文展では特に美人画を一室に集めて展示をしたことからそれが「美人画室」と評され、多くの観客を集めた。一堂に並んだことで、類型的な女性表現がみられたことに対する批判が寄せられた。9そうした批判はとりわけ女性画家に向けられ、新聞、雑誌記事の中には、人気が高かった女性画家に対して男性たちが鬱憤を晴らすかのような論調もみられた。美人画の隆盛は、文展の大衆化とともにあった。そして大衆の支持を得て女性画家たちが隆盛を誇ったようにみえた。しかし男性の審査員や批評家たちが力を持つ展覧会では、彼らの意向に左右されることになった。10回文展では特に関西の女性画家たちが落選したと伝えられた。上村松園も1918年の12回文展には能に主題を得た「生き霊」を描いた《焔》を出品してそれまでの表現を一変させた。一方、池田蕉園が1917年に、河崎蘭香も1918年に相次いで没した。栗原玉葉も1922年に病没する。
・帝展
1919年に帝展が発足すると、当初は美人画は少なかったが、1925年頃から再び美人画が目立って出品されるようになる。鏑木清方も美人画として後世に名高い《築地明石町》(1927年)を描いて帝国美術院賞を受賞するが、自身では美人画の呼称を嫌い、これを「社会画」と位置づけた。帝展重鎮の菊池契月も、自身が女性を描いた絵が美人画とみられることに反論した。すでに地位を築いた男性たちは美人画に背を向けるが、その後帝展では新しい世代が台頭した。女性画家では女子美術学校を卒業し鏑木清方の弟子であった柿内青葉が《十六の春》(1925年、女子美術学校所蔵)で6回帝展に入選すると、翌年には新聞社のカレンダーとして印刷、配布された。大阪の木谷千種(1895–1947年)は6回帝展に《眉の名残》と題した着物から肌が透けて見える豊満な女性像を出品して注目を集めた。
老年にさしかかる上村松園は、ますます能への傾倒を深め、またすでに過去となった明治の風俗を描くことで、現実を離れて理想化した女性像を描いた。度々海外で開かれた日本美術展への出品依頼を受けたのは、そうした理想的な女性像が日本の女性像を海外に提示する役割を期待されたと思われる。さらには1934年には帝展出品作《母子》、1936年には文展招待展出品作《序の舞》が政府買い上げとなる。戦時中に男性たちが戦場に行き母子家庭が増えると、母一人に育てられ、シングル・マザーであった松園の家庭環境も肯定的に捉えられる。1941年には帝国芸術院会員、1944年に帝室技芸員に任じられ、男性画家と遜色ない、あるいはそれ以上のキャリアを築いた。
おわりに
頼りなく儚げな女性を描いた女性画家たちも、現実には独立した画家として生活するために多忙だった。人気を背景に若い女性たちが弟子入りを希望するようになると、自宅を私塾として多くの女性たちに絵の指導をした。池田蕉園の場合には夫の輝方とともに画塾を経営したため、男女の塾生を指導したが、女性画家の画塾では基本的に女性の弟子たちを擁した。木谷千種も蕉園のもとで一時学んでおり、自身では結婚後大阪で画塾八千草会を結成して多くの女性たちを擁し活発に活動した10。基本的に女性たちは結婚前の習い事として通っていたが、千種は1925年には塾を研究所に改組し、展覧会もおこなった。また自身も大阪の女性画家たちと展覧会を組織した。
独身であった栗原玉葉の場合には、画塾が安定した収入源として重要であった。『淑女画報』(7巻3号、1918年3月)では栗原玉葉門下の新年会が盛んである様子を伝えている。弟子達とそれぞれの作品が並んでいる写真を見るならば、どれもよく似ており玉葉のコピーのようである。彼女たちが創造性を発揮するよりもファンとして師の画風を追っていた様子をうかがうことができる。また玉葉は若い女性向け雑誌の口絵も多く手がけた。一方で玉葉自身は女子美術学校卒業生を中心に女性画家たちと研究会、月耀会を1920年に結成し、展覧会を開いている。
若い女性たちが、女性画家たちが描いた理想的な美人に憧れて画塾に集まり、そうした非現実的な女性のイメージを再生産することで、女性だけの世界で「美人画」を楽しんだ。それは男性たちが支配する現実社会から切り離された閉じた世界であった。しかしそうした女性たちによるシスターフッド的な連携が女性画家たちの生活や研究を支えたのであえる。
近世の女性画家および奥原晴湖、野口小蘋については、以下を参照。パトリシア・フィスター『近世の女性画家たち−美術とジェンダー』京都、思文閣出版、1991年。平林彰編『没後100年 野口小蘋』展図録、山梨県立美術館、2017年。仲町啓子「江戸時代の女性画家の研究−実践女子大学香雪記念資料館所蔵品を中心に−」『江戸時代の女性画家』東京、中央公論美術出版、2023年、p.3-106。
2
児島薫「文展開設の前後における『美人』の表現の変容について」『近代画説』16号、p.31-47。
3
文部科学省「学制百年史 三明治初期の女子教育」https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317595.htm
4
金子一夫「明治期中等学校図画教員の研究(6) -東京府-」『茨城大学教育学部教育研究所紀要』第22号、1990年、p.71-80
5
私立女子美術学校に関しては、女子美術大学百周年編集委員会編『女子美術大学百年史』、東京、女子美術大学、2003年、を参照。
6
栗原玉葉については児島薫「女性画家としての栗原玉葉−「女性性」をアイデンティティとして」、五味俊晶編『栗原玉葉』長崎、長崎文献社、2018年、p.228-239
7
吉岡班嶺編『帝国絵画宝典』東京、帝国絵画協会、1918年。
8
坂井犀水「東都の閨秀風俗畫家(上)」『美術新報』13巻6号、1914年4月13日、p.216
9
「美人画室」に関しては、中野慎之「美人画室再考−美人画家の評価と表現」『近代画説』27号、2018年、p.32-53、伊藤たまき「第九回文展の前と後−「美人画」をめぐる諸相」、前掲『栗原玉葉』p.256-271を参照。
10
『女性日本画家木谷千種−その生涯と作品−』池田市立歴史民俗資料館、池田市(2002年10月25日-12月1日)、池田市立歴史民俗資料館、池田市、2002年
11
児島 薫
東京生まれ。実践女子大学教授(美術史)。1985年東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。1987年から1993年まで東京都近代美術館学芸員助手。2007年、ロンドン芸術大学で博士号を取得。著書に『女性像が映す日本: 合わせ鏡の中の自画像』(東京:ブリュッケ、2019年)。その他の著書に「The Changing Representation of Women in Modern Japanese Paintings」(『 Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan』111-132頁所収、菊池裕子編、ホノルル:ハワイ大学出版局)、 「The Woman in Kimono: An Ambivalent Image of Modern Japanese Identity」(『実践女子大学美學美術史學』No. 25 [2011年3月]1-15頁所収)、「近代化のための女性表象ー『モデル』としての身体」( 『アジアの女性身体はいかに描かれたか 視覚表象と戦争の記憶』北原恵編、東京:青弓社、2013年)、「Pictures of Beautiful Women: A Modern Japanese Genre and its Counterparts in Europe, China, Korea and Vietnam」(『Review of Japanese Culture and Society 26(2014年)50–64頁所収』、「女性像が示す近代、大衆、ニッポン 」(『モダン美人誕生 岡田三郎助と近代のよそおい』6-11頁所収、 箱根:ポーラ美術館、2018年 )など。