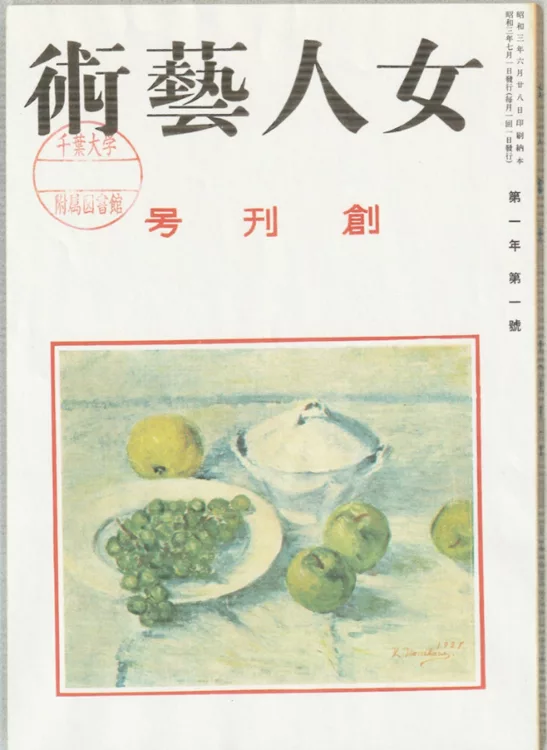上村 松園
日本人画家
上村松園は近代日本における代表的な女性画家である。1948年に女性として初めて文化勲章を受章。また近代以降の美術家の中で作品が重要文化財に指定された女性は、彼女ただ一人である(2023年4月現在)。 松園の作品のほとんどは、女性の姿を描いたものである。松園は、浮世絵の図像を参考としたり、あるいは能などの伝統芸能に主題を求めたりしながら、彼女自身が考える「理想の女性像」を描き出した。
彼女は10代後半から画家として注目を集め始め、後を追う女性画家も数多く出現した。彼女の活躍は、女性を主題とした「美人画」というジャンルが当時の美術界に生まれる契機にもなった。しかし結局のところ、彼女の高い技術力、そして何物にも依存しない、精神的に自立した女性の内面を描写する能力という点では、彼女は同時代の他の作家による追随を許さなかった。
1887年に京都府画学校に入学。翌年同校を退学し、画学校時代の恩師である鈴木松年(1848–1918年)に入門する。1890年、第3回内国勧業博覧会に《四季美人図 》(所在不明)を出品。同作品は英国のコンノート皇子の買い上げとなり、大いに注目を集めた。またより幅広く画を学ぶため、1893年より四条派の幸野楳嶺(1844–1895年)の画塾に通い、1895年の楳嶺没後は楳嶺門下の竹内栖鳳(1864–1942年)に学んだ。1900年、第9回日本絵画協会・第4回日本美術院連合絵画共進会に《花ざかり》(所在不明)を出品、賞を受け画壇に広く認められた。
1907年、第1回文展に《長夜》(1907年、福田美術館蔵)を出品、以降同展に出品を重ねた。ちょうどこの時期、画壇では美人画が隆盛し、美人画は大衆の人気と批評家による非難―女性の外形の美しさを描いただけで内容がない、画中の女性の姿が卑俗である等―とのはざまにあった。こうした現象に呼応するかのように、同時期の松園の作品、例えば《花がたみ》(1915年、第9回文展出品、松伯美術館所蔵)、《焔》(1918年、第12回文展出品、東京国立博物館所蔵)では、それまでの彼女の作品とは異なり、人物の内面の描出に重点が置かれている。その後も細部の緻密な描写に注力した《楊貴妃》(1922年、第4回帝展出品、松伯美術館所蔵)など、さまざまな表現を試みた。 こうした試みの一方で、画壇での松園の地位は着実に高まっていった。1924年には帝展の委員となり、皇族や財閥などからの依頼画の数も次第に増加した。
1934年、母が没した。母は松園を女手一つで育て、松園が画業の道に進むことを後押しした存在である。以降、《母子》(1934年、第15回帝展出品、東京国立近代美術館所蔵、国宝・重要文化財[美術品])など、過去の風俗の中に亡き母への追慕の念を託したものが見られるようになった。またこの1930年代は松園芸術の集大成とも言うべき大作が次々と生み出された時期でもある。松園には珍しく現代風俗に取材した《序の舞》(1936年、文展招待展出品、東京芸術大学所蔵、国宝・重要文化財[美術品])、彼女の長年の余技である謡曲を制作に生かした《草紙洗小町》(1937年、第1回新文展出品、東京芸術大学所蔵)などである。
晩年にあたる1940年代は小品の数が増えるが、過去の市井の人の暮らしを取り上げた《晩秋》(1943年、関西邦画展出品、大阪市美術館所蔵)をはじめ優品は多い。
「19世紀から21世紀の日本の女性アーティスト」プログラム