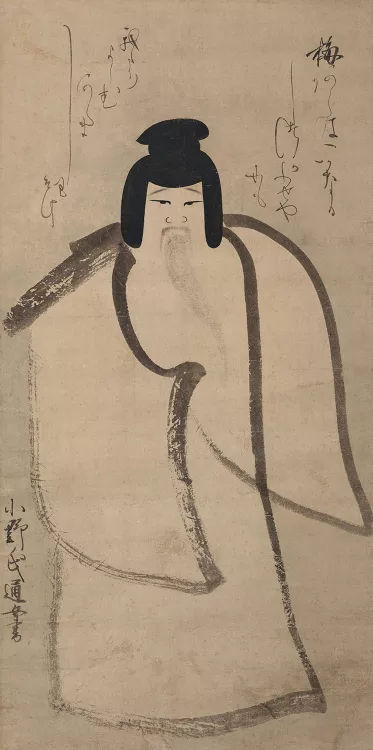林 三從
日本人アーティスト、オーガナイザー、ディレクター
岡山県備前市生まれ。ノートルダム清心女子大学英文科(岡山市)に入学するが、1年で中退して上京。本格的に絵画制作を始める。帰郷後、岡山大学の教職にあった竹内清(1911–2008年)を知り、その紹介で、1920年代にパリでアメデエ・オザンファン(1886–1966年)とシャルル=エドゥアール・ジャンヌレ(ル・コルビジェ/1887–1965年)によるピュリスム運動に関わった経歴を持つ坂田一男(1889–1956年)が組織したA・G・O第2回展(1953年3月)に出品。また竹内教室を訪ねるうちに岡山大学教育学部美術教室の者達と交友が始まり、彼らが組織した前衛的なグループ「サロン・ド・モア」で第2回展(1958年)からメンバーとなり、以後同展にかかさず出品。さらにその発展的グループである1963年の「岡山青年美術家集団」結成にも加わり出品を続ける。
サロン・ド・モアの終盤からオブジェ作品に取り組むが、1963年12月第2回岡山青年美術家集団展の頃から木や段ボール箱を素材に、内と外を異なる色彩で塗り分けたり、関連を想起させたりする簡単な記号を配したBOX型の立体作品を手がける。1964年8月スルガ台画廊(東京)、同年12月内科画廊(東京)での個展において、BOX作品を発表。立方体の案内状に始まり、さらに多様に展開させる。
1965年3月東京・椿近代画廊でネオダダ系の作家を中心に39名によるグループ展「Big Fight」に出品。主導者であり、同時代の日本を代表するアーティストの篠原有司男(1932年–)や吉村益信(1932–2011年)、三木富雄(1937–1978年)などと交友を持つ。
また1962–1964年に帰国したオノ・ヨーコ(1933年–)の存在を知り、草月会館や内科画廊でのパフォーマンス作品《モーニング・ピース》(1964–1965年)《カット・ピース》に参加》(1964年)に参加。彼女の詩集『グレープフルーツ』を入手するなどその活動に大きな感化を受ける。また塩見允枝子(1938年–)と旧知であったこともあり1965年、東京のクリスタル画廊で秋山邦晴(1929–1996年)ディレクションによる「フルクサスウィーク」で塩見や小杉武久(1938–2018年)とパフォーマンスを行う。
1970年代以降は《EVENT》と題してクレーン車で吊り上げた車を落下させ炎上破損した車を展示したり、1971年頃から取り組んだ《GREEN REVOLUTION》プロジェクトでは、セスナ機から大根などの種をまいたり、種を蒔育の方法を書いた指示書を郵便で送付したりといったコンセプチャルで多角的なプロジェクトを実施している。
1970年代半ばから、林の表現はパフォーマンス的な要素を強め、演劇や音楽などの領域と次々とコラボレーションしていく。そうしたなかで松澤宥(1922–2006年)、寺山修司(1935–1983年)、小杉などとの交友を広げる。1987年から1997年まで拠点を置く備前市において総合アートイベント「備前アートフェスティバル」を展開し、制作者に限らず、オーガナイザー、ディレクターとして自身の表現活動の領域を広げて行く。
こうした同時代の日本においては過激とも言える表現活動と並走して、林は、郷里の備前市で、おそらく1950年代の半ばから逝去の年まで子供達を対象とした美術教室を継続させていた。
「二つの脳で生きる:1960年代〜1990年代、ニューメディア・アートで活躍した女性アーティストたち」プログラム
© Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, 2024